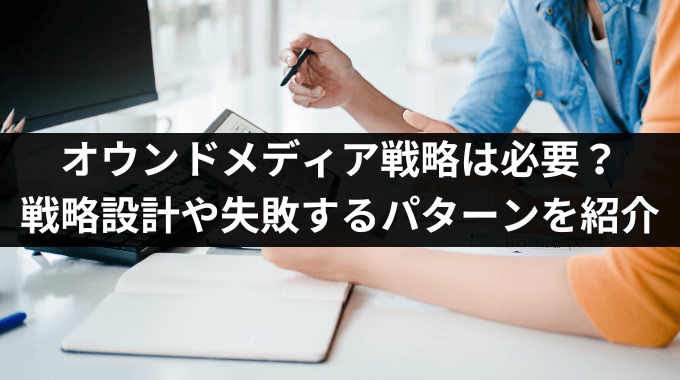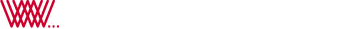「オウンドメディア戦略とは何か?」
「効果的なオウンドメディア戦略設計は?」
オウンドメディア戦略とは、自社の目的達成に向けて、オウンドメディアを効果的に活用するための具体的な計画です。
本記事では、オウンドメディア戦略の重要性や設計のポイント、よくある失敗パターンとその対策について詳しく解説します。
また、運営にかかるコストや更新頻度、他のマーケティング施策との連携方法など、実践的な内容も紹介してます。
オウンドメディアの運営を検討している方や、既に運営しているが効果に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
オウンドメディア戦略とは
オウンドメディア戦略とは、自社の目的達成に向けて、オウンドメディアを効果的に活用するための具体的な計画です。
多くの企業がオウンドメディアを始めていますが、どのように運営すればよいか悩む方も少なくありません。
そこで重要になるのが戦略です。戦略を立てることで、目標に向かって効率的に進むことができます。
具体的には、目的の明確化、ターゲット設定、KPI設定、コンテンツ計画などを含みます。
例えば、「30代女性向けに美容情報を発信し、3か月で月間PV10万を達成する」といった具体的な目標を立てることが戦略の一部となります。
このように、オウンドメディア戦略は目標達成への道筋を示す重要な要素なのです。
オウンドメディア運営にはなぜ戦略が必要?

オウンドメディア運営において戦略が必要な理由としては、目標達成の明確化、リソースの最適化、競争優位性の確保、KPIの設定と効果測定が挙げられます。
それぞれの理由について詳しく解説していきます。
目標達成の明確化
オウンドメディアの戦略は、目標達成を明確化するために必要不可欠です。
なぜなら、戦略があることで具体的な道筋が見え、効果的な施策を実行できるからです。
ただコンテンツを発信するだけでは、効果的な成果を得ることは難しいのです。
戦略を立てることで、目的や目標が明確になり、どのような行動をとるべきかが分かりやすくなります。
具体例として、リード獲得を目的としたオウンドメディアの場合、「3ヶ月後に月間リード数100件」といった具体的な目標を設定し、そこから逆算して必要な施策を考えることができます。
これにより、日々の運営に明確な方向性が生まれ、効率的に目標達成に近づくことができるのです。
リソースの最適化
戦略なしでオウンドメディアを運営すると、人員や予算、時間といったリソースが無駄に消費されてしまう可能性が高くなります。
具体例として、社内の専門知識を持つ人材を起用したり、外部リソースを適切に組み合わせたりすることで、効率的なコンテンツ制作が可能になります。
また、タスクの整理やスケジュール管理を徹底することで、少数精鋭のチームでも質の高い運営ができるでしょう。
このように、オウンドメディアの戦略を立てることで、リソースの最適化が実現できます。
競争優位性の確保
オウンドメディアの戦略は、競争優位性を確保するために必要です。
なぜなら、戦略的なアプローチによって、他社との差別化を図り、独自の価値を提供できるからです。
例えば、自社の専門知識や独自の視点を活かしたコンテンツを発信することで、ターゲット層に強く訴求できます。
具体的には、ある企業が業界の専門的なトピックについて深掘りした記事を定期的に公開し、そのナレッジを武器に競合他社との差別化に成功した事例があります。
KPIの設定と効果測定
オウンドメディアの戦略は、KPIの設定と効果測定を適切に行うために不可欠です。
それは、戦略があることで、目標達成に向けた具体的な指標を定め、その進捗を正確に把握できるからです。
たとえば、「月間PV10万件」や「CVR3%」といった具体的なKPIを設定し、Google アナリティクスなどのツールを使って定期的に測定することで、目標達成度を客観的に評価できます。
また、「半年後までに月間新規リード100件獲得」のような期限付きの目標を立てることで、進捗管理がしやすくなります。
このように、オウンドメディアの戦略に基づいたKPI設定と効果測定は、目標達成への近道となるのです。
オウンドメディアの戦略設計
オウンドメディアの戦略設計において重要なポイントは、以下の通りです。
- 明確な目的設定
- KPIの設定
- ターゲットペルソナの設定
- 競合分析の実施
- サイトコンセプトの設計
- 流入経路の設計
- PDCAサイクルの設計
それぞれの要素について詳しく解説していきます。
明確な目的設定
オウンドメディアの戦略設計で最も重要なのは、明確な目的設定です。
なぜなら、目的が曖昧だとコンテンツの方向性がぶれやすく、効果的な運営ができないからです。
具体的には、以下のような目的を設定することが大切です。
| 目的の例 | 詳細 |
|---|---|
| 認知向上 | 自社ブランドの知名度を上げる |
| 売上拡大 | 商品やサービスの販売を増やす |
| リード獲得 | 見込み顧客の情報を集める |
| 採用強化 | 求職者へのアピールを行う |
例えば、「3か月後までに月間問い合わせ数を50件にする」といった具体的な数値目標を立てることで、戦略の方向性が明確になります。
KPIの設定
KPIがあることで、目標達成に向けた進捗状況を把握し、最適な改善策を講じることができます。
具体的には、以下のようなKPIを設定する必要があります。
| フェーズ | KPI例 |
|---|---|
| 立ち上げ期 | コンテンツ数、PV数 |
| 成長期 | UU数、CV数 |
| 安定期 | リード獲得数、ROI |
たとえば、立ち上げ期では「月間20本の記事を公開する」というKPIを設定し、成長期では「月間UU数を10,000に増やす」といった具体的な数値目標を立てることで、戦略の方向性が明確になります。
- 最終目標(KGI)を明確にする
- KGI達成に必要な要因(KFS)を特定する
- KFSに基づいて具体的なKPIを設定する
このように、オウンドメディアの成功には、フェーズに応じた適切なKPI設定が重要になります。
ターゲットペルソナの設定
ターゲットペルソナの設定は、オウンドメディアの戦略設計において非常に重要です。
それは、ターゲットとなる顧客の特性や行動パターンを深く理解することで、より的確なアプローチができるからです。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 年齢 | 32歳 |
| 性別 | 女性 |
| 職業 | 会社員 |
| 年収 | 500万円 |
| 居住地 | 東京都世田谷区の賃貸マンション |
| 家族構成 | 独身 |
| 趣味 | ヨガ(週1回)、カフェ巡り、旅行 |
| 悩み | 仕事と私生活の両立、将来の結婚・出産 |
| 情報収集 | Instagram、YouTube、ビジネス系ポッドキャスト |
こうした具体的なイメージを持つことで、オウンドメディアの内容や発信のタイミングなどをより適切に設計できます。
また、Instagram や YouTube を活用した情報発信や、通勤時間帯にチェックしやすいコンテンツを考えるなど、ターゲットの生活リズムに合わせたアプローチが可能になります。
競合分析の実施
競合分析を行うことで、自社の強みを見出し、差別化を図ることができます。
その理由は、競合他社の動向や市場トレンドを把握することで、自社のポジショニングを明確にできるからです。
具体的には、競合他社のコンテンツ、キーワード戦略、デザイン、ユーザー体験などを分析します。
例えば、競合サイトの人気記事や流入キーワードを調べることで、読者のニーズや関心を把握できます。
また、競合サイトのデザインや構成を参考にしつつ、自社の独自性を出す工夫を考えることもできます。
このように、競合分析はオウンドメディアの方向性を定める上で重要な指針となります。
サイトコンセプトの設計
サイトコンセプトを明確に定めることで、ユーザーに価値を伝えやすくなり、一貫性のあるコンテンツ制作が可能になります。
具体的には、5W1Hのテンプレートを使ってコンセプトを設計します。
以下の表は、「働く女性のキャリアを応援する」というコンセプトを5W1Hのテンプレートを使ってより具体的に示したものです。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| Who(誰に) | 25〜45歳の働く女性、特に管理職を目指す層や転職を考えている層 |
| What(何を) | キャリアアップに関する情報、スキルアップのためのオンライン講座、ロールモデルのインタビュー記事 |
| When(いつ) | 平日の昼休みや通勤時間、週末の自己啓発の時間 |
| Where(どこで) | スマートフォンやPCから閲覧可能なウェブサイトやアプリ |
| Why(なぜ) | 女性の社会進出を促進し、キャリアにおける男女格差を縮小するため |
| How(どのように) | 専門家による記事執筆、成功した女性へのインタビュー、オンラインセミナーの開催、Q&Aフォーラムの運営 |
この表を基に、サイトの具体的なコンテンツや機能を決定し、ターゲットユーザーのニーズに合わせたサイト設計を行うことができます。
このように、サイトコンセプトの設計は、ユーザーに響くコンテンツを生み出すための重要な基盤となります。
流入経路の設計
適切な流入経路を設計することで、ターゲットユーザーを効果的に集客し、コンバージョンにつなげることができます。
その理由は、ユーザーの行動パターンや関心に合わせた導線を用意することで、自然な形でメディアへの流入を促せるからです。
具体的には、SEO対策による検索エンジンからの自然検索流入、SNSを活用した流入、広告を使った流入などが挙げられます。
例えば、ターゲットユーザーが使用しそうなキーワードを意識したコンテンツ作成でSEO流入を増やしたり、Instagram等のSNSで魅力的な投稿を行い、そこからメディアへの誘導を図ったりすることができます。
このように、ユーザーの特性や目的に合わせて適切な流入経路を設計することで、効果的なオウンドメディア運営が可能になります。
PDCAサイクルの設計
適切なPDCAサイクルを設計することで、継続的な改善と目標達成が可能になります。
具体的には、まず目標設定(Plan)を行い、それに基づいてコンテンツを制作・公開(Do)します。次に、アクセス解析などで効果を測定(Check)し、その結果を踏まえて改善策を検討・実施(Action)します。
例えば、月間PV数を10%増加させる目標を立て、新しいコンテンツを公開し、アクセス数の変化を確認して、人気のあったテーマに注力するといったイメージです。
このように、PDCAサイクルの設計は、オウンドメディアの成長と改善を支える重要な要素です。
オウンドメディア運営でよくある失敗パターン

ここでは、オウンドメディア運営でよく見られる4つの失敗パターンとその対策について解説します。
明確な目的や戦略がないまま運営を開始してしまうケース
明確な目的や戦略がないまま、オウンドメディアの運営を始めてしまうのは、よくある失敗パターンの一つです。
このような状況では、コンテンツの方向性がぶれやすく、結果として効果的なメディア運営ができません。
なぜなら、目的が定まっていないと、どのような内容を発信すべきか、誰に向けて情報を届けるべきかが不明確になるからです。
例えば、単に競合他社が行っているからという理由だけで安易に始めてしまうと、コンテンツの更新が滞ってしまったり、独自性に欠ける内容になりがちです。
したがって、オウンドメディアを始める前に、なぜ運営するのか、どのような成果を期待するのかを明確にすることが大切です。
責任者が明確でない、必要な人材が確保できていない運営体制
オウンドメディアの運営体制に責任者が明確でなく、必要な人材が確保できていないことは、失敗の大きな原因となります。
なぜなら、責任者不在により意思決定が遅れ、戦略的な運営ができないからです。また、人材不足は更新頻度の低下や低品質なコンテンツの増加につながります。
例えば、責任者が不在のまま複数の部署が関わり、統一感のないコンテンツが乱立してしまったり、専任の担当者がおらず、他の業務の合間に更新するため、記事の質が低下し、読者離れを招くことがあります。
したがって、オウンドメディアを成功させるには、明確な責任者を決めて、必要な人材を適切に配置することが重要です。
ユーザーへの価値提供よりも自社の宣伝を優先してしまう
オウンドメディアの運営で、ユーザーへの価値提供よりも自社の宣伝を優先してしまうのは、大きな失敗につながります。
この問題が起こる理由は、短期的な成果を求めるあまり、ユーザーのニーズを無視してしまうからです。
しかし、このアプローチではユーザーの信頼を得ることができず、結果的に効果的なブランディングや顧客獲得ができません。
なので、自社の宣伝は控えめにし、ユーザーの関心や問題に寄り添ったコンテンツを発信するようにしてください。
短期間での成果を求めすぎてしまう
オウンドメディアの運営で短期間での成果を求めすぎてしまうのは、失敗につながる大きな要因です。
成功には時間がかかるものなのに、早急な結果を期待してしまうと、モチベーションが下がり、継続が難しくなってしまいます。
例えば、ある企業では1ヶ月で1万アクセスを目標に掲げましたが、達成できずに更新をやめてしまいました。また、3ヶ月で売上がないので運営を中止してしまったケースもあります。
このように、短期間での成果を求めすぎて失敗することもあるので、短期的な数字にとらわれず、コツコツとコンテンツを積み上げていくことが大切になります。
オウンドメディア戦略に関するよくある質問
オウンドメディアの運営にかかる平均的なコストはどのくらいですか?
オウンドメディアの運営にかかる平均的なコストは、月額20万円〜80万円程度です。
これは、オウンドメディアの規模や運営方法によって大きく変動します。
主な費用の内訳としては、サイト維持費(サーバー代、ドメイン代)、マーケティング費、分析・改善費、コンテンツ制作費などが含まれます。
例えば、小規模なオウンドメディアの場合、サイト維持費が月数千円程度、コンテンツ制作を自社で行い、外部のSEO対策サービスを利用するなどで月10万円程度に抑えることも可能です。
一方、大規模なオウンドメディアでは、専門家によるコンサルティングや高品質なコンテンツ制作を外注することで、月100万円を超える場合もあります。
オウンドメディアの記事の更新頻度はどのくらいが理想的ですか?
オウンドメディアの理想的な更新頻度は、週に1〜2回程度です。
この頻度が理想的な理由は、検索エンジンの評価を高め、ユーザーのリピート率を向上させるためです。
定期的な更新により、サイトの鮮度が保たれ、検索結果で上位表示されやすくなります。
具体例として、オウンドメディアを立ち上げたばかりの場合は、週に2〜3記事の更新が望ましいとされています。
一方で、成長期に入ったメディアでは、週1〜2記事の更新でも十分な効果が得られます。
ただし、更新頻度よりもコンテンツの質を優先することが大切です。
オウンドメディアと他のマーケティング施策をどのように連携させるべきですか?
オウンドメディアは、SNS、メールマガジン、広告などの他のマーケティング施策と積極的に連携させるべきです。
なぜなら、相乗効果を生み出し、マーケティング全体の効果を最大化できるからです。
具体例として、SEOで上位表示を達成した記事を広告のランディングページとして活用したり、オウンドメディアの更新情報をSNSで拡散したりすることが挙げられます。
また、メールマガジンでオウンドメディアの記事を紹介し、読者を誘導することも効果的です。
コンテンツ制作を内製と外注のどちらで行うべきですか?
コンテンツ制作は、内製と外注を組み合わせて行うのが理想的です。
内製では自社の強みを活かした独自性の高いコンテンツが作れる一方、リソースの確保が課題となります。
また、外注では専門的なスキルを活用できますが、コストがかかり、ノウハウの蓄積が難しくなります。
具体例として、戦略立案や重要な記事は内製で行い、定期的な更新や専門性の高い記事は外注するという方法があります。
これにより、自社の強みを活かしつつ、効率的にコンテンツを制作できます。
まとめ
オウンドメディア戦略は、自社の目的達成に向けて効果的にメディアを活用するための計画です。
戦略を立てることで、目標に向かって効率的に進むことができ、リソースの最適化や競争優位性の確保が可能になります。
- 明確な目的設定
- KPIの設定
- ターゲットペルソナの設定
- 競合分析の実施
- サイトコンセプトの設計
- 流入経路の設計
- PDCAサイクルの設計
オウンドメディアを成功させるためには、明確な目的と戦略を立て、適切な運営体制を整え、長期的な視点で取り組むことが重要です。
W-ENDLESSでは、コンテンツSEOにおいて、医療系や金融系など、上位獲得が難しいYMYLジャンルでの成果事例があります。以下のリンクで、詳しくまとめているので、併せて確認してください。